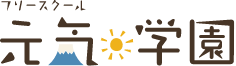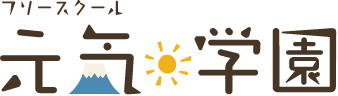生徒たちの生活をみていると、協力しあうことが、苦手な子が多いことに気付きます。
生徒たちの生活をみていると、協力しあうことが、苦手な子が多いことに気付きます。
趣味の話や好きなことをして集うことはできても、お互いにひとつの目的を達成するために、助け合うということが苦手というより、したことがないのだと思います。
また、友達との横の関係だけでなく、先輩を助けたり、先生や親の手助けをしたりと、縦の関係をつくることも、未経験です。
人は、4~5才くらいになると、集団遊びをし始めます。
集団遊びでは、1人遊びや2、3人遊びでは必要のなかった、「我慢」をして相手を喜ばせたり、相手の意図を読み取って「従う」ことをしないと一緒に遊べません。互いに協力しあわないと遊びが成立しないのです。
進化心理学的な観点から見ると、人は、よりよい協力者を得るために、互恵的利他行動による仲間さがし、さらにそれを安定化させるTFT戦略(しっぺ返し行動)を行います。
互恵的利他行動とは、互いに恩恵を与え合い、自分だけでなく相手に利益があるようにふるまうこと。
親切をしてあげたら、それに対して、親切をかえしてくるかどうかで、協力者か非協力者かを判断していきます。
なんだか、難しいけれど、簡単に言うと、「親切とその恩返し」で仲間を集めていくということです。
TFT戦略というのは、互恵的利他行動をとらなければ、しっぺ返しをする。
相手の態度と同じ態度を繰り返します。
だから、相手に協力をしたのに、協力して返してこなければ(非協力)、次には、自分も非協力の態度で返すので、しっぺ返しを食うという事。
こういう行動は、いじめ問題とも関連しています。
子どもたちに学んでほしいのは、集団の中では、互恵的利他行動をおこすかどうかで、協力者かどうか、仲間かどうかを判断しあっているということ。
(驚くことに、人間だけでなくグッピーでも、こうした仲間かどうかの判断をしているのですよ!!そ~んな科学論文があります。)
年齢が上がるにつれて、その集団での幸福や利益を考えて行動していかなければいけなくなっていきます。
例えば、家族の幸せを考えることもですし、また、会社に勤めたら、その会社の得になるように働くということです。
それが、当たり前の感覚としてもっていなければ、周りとは協力関係は結べません。協力関係を結べないということは、仲良くなれないだけではなく、敵をつくることにもなってしまいます。
「どうして、僕がやらなきゃいけないんだ」
「手伝うのは面倒だから、知らんぷりをしていよう」では、喧嘩が始まり、一緒に居られませんよね(^^;)。
ところが、集団での利害関係が一致する、協力行動を強く望まれる年齢、それは、年が大きくなるということですが、上になればなるほど、協力関係を作るのが難しくなります。
協力関係の構築にも、「今その時」という適時性があるのではないかと思います。
10代のうちに、人と仲良くする練習をしっかりしておきたいものです。